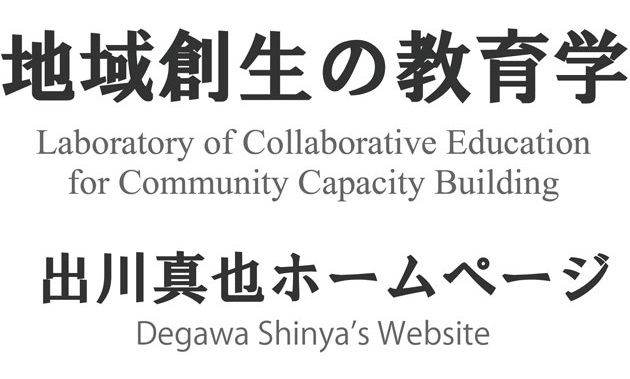新聞等執筆記事
河北新報『座標』 平成22年1月~6月(全6回) 執筆:出川真也(単著)
6「ムラ仕事再考」
2010年6月22日を加筆修正


【概要】
おじいちゃんたちにいろいろ話を聞いていると、かつてのムラの仕事というのは、各個人が選り好みできるようなものではなかった。最初から定められ分担されて、受け継ぎ担うことが求められた。しかしそれはそれでやりがいを感じたもののようだ。それは身近なムラ人たちの切実なニーズがあり、じかに目に見え感謝されるものだったからではないだろうか。
5「ふるさと学習」
2010年5月25日を加筆修正


【概要】
ファームステイとかグリーンツーリズムとか、横文字で大げさにとらえなくても、取り組み自体はそれほど複雑で難しいものであるようには思えない。要は都会から子ども達(だけに限らなくてもよいわけだが)が農山漁村を訪れ、地域に住む人々とのコミュニケーションを通じながら暮らしや文化、自然を学んでいく。地元住民もまたそのようなコミュニケーションを通じて農山漁村の暮らしや生業を元気にしていこうとする、ということだ。「ふるさと学習」としてとてもシンプルで素朴な試みであるといえよう。その大切なメッセージを見つめ直してみたい。昨今声高に叫ばれている行政や業界の本筋から外れた指導やアドバイスに惑わされないためにも。
4「ムラへ向かう若者たち」
2010年4月20日を加筆修正


【概要】
NPO法人地球緑化センターによる緑のふるさと協力隊研修の講師に招かれ、山梨県のある山村地域を訪れた。緑のふるさと協力隊とは、主に20代から30代の若者たちが各地の農村や山村に派遣され、1年間暮らしながら地域の活動に従事する活動だ。今年の協力隊員は50名あまり。背景は様々な若者たちが、純粋に田舎にあこがれ、その暮らしに興味を持ち、不安を抱えながらも素直にこの活動を志願してきている。こうした若者達がムラに入ることでどのような可能性が生まれようとしているのだろうか?
3「地域固有の価値を見つめなおす」
2010年3月27日を加筆修正


【概要】
時代とともにめまぐるしく変化する反面、世界中同じような風景が広がる都市では様々な歪が指摘されて久しい。しかし視点を変えれば、解決の答えの一端は地方の田舎(「ムラ」)にこそあるのではないかと思えてしまう。そのような発想からムラをもう一度歩いて見つめ直してみたい。そのムラ固有の暮らし方、他では通用しないかもしれないけど、そこでしか通用しないものこそが面白かったりするのではないだろうか。2つの異なる視点からムラのあり方を再考する。
2「最上川流域から考えるムラを蘇らせる兆し」
2010年2月23日を加筆修正


【概要】
最上川流域の農山漁村を訪ね歩いてみると同じような境遇のムラを数多く見かける。だが山形のムラは、まだまだかつてのその地に住まうための営み、知恵、技術を脈々と受け継いでいる。過疎化少子化だ、担い手がいないと言われて久しいが、今そこに住むお年寄りたちは元気に日々の暮らしを営んでいるものなのである。そうはいっても孤立無援のままではいわゆる「限界集落」と呼ばれる地域衰退を招くことになるだろう。それは、自然と織りなしあいながら形成されたムラの成り立ちの物語が忘れ去ることであり、次の時代に受け継ぐべき本当に豊かに生きるための知恵や技術を失うことを意味するのではないか。筆者のみならずムラの暮らしに接したことのある東北人、いや日本人ならばだれでも本能的に感じ取るのではないだろうか。
1「地域独自の多様な経験から普遍を俯瞰する」
2010年1月26日を加筆修正


【概要】
東北地方を回っていると各地の方言や言い回しの豊かさにいつも驚かされる。東北に来て10年以上たってもその新鮮な印象は変わらない。方言の豊かさは、その地域に根差した自然環境、生活文化、紡いできた歴史の多様性と通底するものだと思う。 月山の周囲の村に住むマタギのおじさんたちの里山に棲む動物たちの話、最上川の川漁師たちの水流や風向きと操船の話、山里のおばさんたちの郷土料理の話などを聞く時、特にそう思う。このような話は方言とその地域独特の言い回しでしか語り得ないものなのだ。そこには標準語では説明不可能な機微があり、確かな暮らしの息づきを感じるのである・・・。
山形新聞『日曜随想』 2005年1月~11月(全10回) 執筆:出川真也(単著)
10「里の心を伝えること」
2005年11月27日掲載を加筆修正


【概要】
抑圧することなく里の人々と外部者が協働し共に創りあげていくためのメッセージはどのように生み出せるのだろうか?山形の山村の事例から考察する。
9「里の若者達」
2005年10月23日掲載を加筆修正


【概要】
将来像がなかなか描けない時代だからこそ、地域作りにかかわりながら夢を模索し、自己実現を目指そうとする彼らの純粋な姿勢には共感する。とかく若者達が集うと何か不穏な雰囲気を感じさせる今の風潮だが、地域がその活動を温かく見守り真摯にサポートしていくことで、里の若者達は地域に根ざして真に光を放つことができるのではないだろうか?この意味において大人の役割は極めて大切で大きいといえるのである。
8「里と里をつなぐ力」
2005年9月18日掲載を加筆修正


【概要】
今「地域づくり」という言葉に幅広い意味が含まれようとしている。自分たちの住む地域が他の地域とも結びついているという意識が芽生えはじめている。山形県最上地方と庄内地方の里づくり活動をネットワーク化し活性化するNPO活動の取り組みを紹介する。
7「里づくりを支えるもの」
2005年8月14日掲載を加筆修正


【概要】
里づくりのためには実に多くのサポートが必要だ。地元住民はもちろん、参加し応援してくれるヨソモン、邪魔をせず一歩引いて手堅く時には柔軟な支援を行うまじめな行政、その他企業や教育機関等、本来業務の先にこうした地域を支える責務があるのではないかと考える。里づくりを支えることの一端を山形の山村の事例から紹介する。
6「ヨソモンと里人」
2005年7月10日掲載を加筆修正


【概要】
歴史上、東北の村々は必ずしも閉鎖的なムラ社会であったというわけではなかった。どこの農山村も多かれ少なかれ「ヨソモン」との交流をもちながらその暮らしや文化を育んできたことだろう。しかしかつて活発だったヨソモンとの交流も高度経済成長時代以降は下火になってしまったようだ。それは物質的なものよりはむしろ感情的な面で都市と農山村との間で大きな断絶が生み出してしまったのではないかと筆者などは思う。だが今、草の根的な住民活動の中でヨソモンと里人の新しい関係が生み出そうとしている。
5「里で創り出す『形』」
(2005年6月5日掲載を加筆修正


【概要】
山里での仕事は、やり遂げたとき何やら特別な達成感を感じるものと最近思うようになった。山の手入れ、道普請、炭焼き窯作り、農作業、郷土食作り・・・、数え上げるときりがないが、やり終えた後、ある特殊な感動を覚えるものなのだ。炭焼き窯と田植えの経験から山里仕事の醍醐味について考察する。
4「里山と山菜料理」
2005年5月1日掲載を加筆修正


【概要】
雪国の春はせわしなく過ぎてしまうのが常だ。山形の山里は例年4月半ばまで雪が残る。そして雪が消えたところからカタクリの花が咲き出すのを皮切りに、コブシ、マンサク、梅、桜、スモモ・・・など、花という花がほぼ同時に咲き乱れる。そして筆者も待ち遠しい山菜の季節となるのである。山村の知恵と技術の粋とも言える里山と山菜について触れる。
3「里の子ども達から学ぶこと」
2005年3月27日掲載を加筆修正


【概要】
山村の小さな集落で育つということから生じる親の不安もある。保育所から中学卒業まで、ずっと同じメンバーで兄弟のようにして育ってしまうことは、必ずしも良いことばかりではないというのである。 一方で、こうした地域集落だからこそすばらしい原体験を子ども達に与えることができるのではないか、地域にはその独自の価値があり、原体験を子ども達に積ませていくことが大切ではないかという動きもある。 このような活動のメッセージを受け止めて地域の「よさ」に目を向け、将来の夢を地域社会の中に語る子ども達も出て来た。こうした子ども達の夢にどう答えていくことが出来るか、地域の大人達の真価が今まさに問われていると言える。
2「またぎと里山」
2005年2月20日掲載を加筆修正


【概要】
山形県北部に位置する山村、戸沢村角川地区。冬のこの期間は何もかも雪に埋まる。角川の人々も家の中で薪ストーブにあたりながらひっそりと暮らすのが常だが、この季節こそ元気に山を駆け巡る人々がいる。またぎ(猟師)のおじさん達だ。彼らの実践に裏打ちされた確かな知恵と技術の一端を紹介する。
1「山村の人々から学ぶ」
2005年1月15日掲載を加筆修正


【概要】
山形県最上地方の最深部、戸沢村角川地区に来て2年が経とうとしている。長野県北部の農村集落で育った私は、当時の子どもとしては珍しく里山や川で一日中遊び歩く原体験をもつことができた。だが、少年時代の最後の日々には、開発に伴う故郷の変化を目の当たりにすることになった。それは自然環境だけではなく地域の人のつながりをも変えてしまうものだったと言える。筆者が近年住み込んだ山形のとある山村の暮らしぶりとそれを生かした取り組みから学ぶことについて考えてみたい。